東京の無痛分娩助成は“声の大きい人だけが得する”制度なのか? 医師が語る実態と課題 | 産婦人科医・麻酔科医 市村先生vol.02
『無痛分娩PRESS』の監修をお願いしている市村先生に出産に関する様々なことについて答えてもらうシリーズ。今回は「東京都の無痛分娩助成制度」についてお話を伺いました。制度の概要はもちろん、実際に現場で感じる課題や疑問、そして“制度の先”にあるべき医療のあり方まで──産婦人科医でもあり麻酔科医でもある市村先生が、専門家としての立場から率直に語ってくれました。
【本記事についてのご注意】
本記事は、2025年1月に行ったインタビューをもとに構成されています。掲載内容には、当時の制度設計や社会情勢に基づく発言が含まれており、記事公開時点(2025年7月)と制度の運用状況や対象条件が異なる場合があります。特に、無痛分娩への公的助成制度の適用範囲や今後の拡大可能性については、最新の公的情報をご確認ください。
また、本記事では現場の医療従事者の視点から率直な意見や課題提起が語られており、内容には一部センシティブな表現や制度への批判を含む部分もあります。これらは個人や特定の団体を非難する意図ではなく、より安全で公正な医療体制の在り方を読者の皆さまとともに考えるための一助として掲載しています。ご理解のうえお読みいただけますと幸いです。
市村先生Profile

無痛分娩において日本トップクラスのクリニック『鎌ヶ谷バースクリニック』の診療部長。2008年に聖マリアンナ医科大学を卒業。東京医科歯科大学産婦人科に入局。関連施設の周産期センターに勤務後、東京女子医科大学東医療センター麻酔科に入局。 2016年に鎌ヶ谷バースクリニックを設立。 自身も産科麻酔医として診療に従事するとともに、東京女子医科大学東医療センター麻酔科講師として後進の指導、育成に力を入れる。
東京都の無痛分娩助成制度、なぜ“都内限定”なのか?
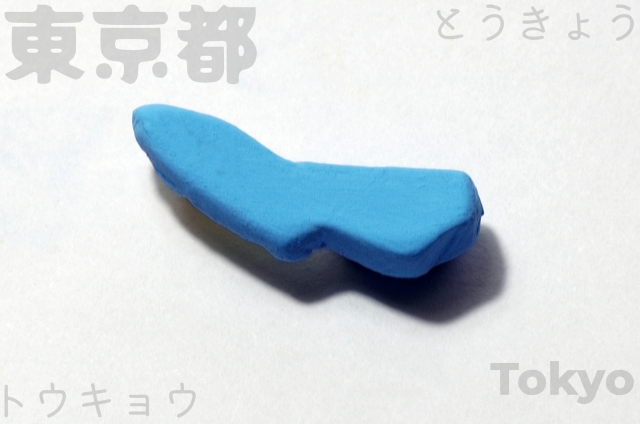
interviewer:今回は、2025年10月から東京都が開始する「無痛分娩への助成制度」について、実際の医療現場に関わるお立場から、いろいろとお話を伺えたらと思います。まずは制度の概要について教えていただけますか?
市村さん:はい。これは、東京都の小池都知事が進めている施策で「都民ファーストの会」が中心となって進めているものです。2025年10月から「試験的に」というニュアンスでスタートする予定です。
interviewer:どのような条件で助成が受けられるのでしょうか?
市村さん:助成の対象となるのは、都内の病院で無痛分娩を行う、かつ住民票が東京都にある妊婦さんに限られています。いわゆる“里帰り出産”で他県に移動して出産する場合には適用されません。
interviewer:ということは、例えば東京に住民票がある人が、実家のある千葉や埼玉で出産した場合は対象外になるんですね。
市村さん:そうなんです。逆に、千葉県に住んでいる方が東京の病院で産む場合も対象にはなりません。あくまで「東京都民が、東京都内の病院で産む」場合だけ。これがまた、医療現場から見ても少し不可解でして。
interviewer:なるほど。それは確かに現場感覚とズレがあるように感じます。
市村さん:はい。実際、東京都の端っこに住む方、たとえば練馬区や多摩地域に住んでいる方の中には、地理的に近い埼玉の病院を選ぶ方も多いんです。そうした現実を考えると「東京都内のみが対象」という制度設計には、やや無理があるように思いますね。
interviewer:今後の制度の拡大などについても議論されているのでしょうか?
市村さん:はい。2025年4月以降に制度が拡大される可能性もあるようです。たとえば「住民票は東京にあるけれど、他県で出産する場合も助成対象とする」といった方向性ですね。全国に広げるのは難しいとしても、東京都がやるのであれば、それくらい柔軟な制度設計をしても良かったのではと思います。
interviewer:現場の声から見ると「とりあえずやりました感」が出てしまっているように聞こえますね。
市村さん:その通りです。助成制度自体はありがたい話だと思うんですけど「なぜ無痛分娩だけを対象にしたのか?」という点では、やはり説明がつきにくいというのが率直な印象ですね。
助成制度の裏にある“選挙”と、“誰のための制度か”という疑問
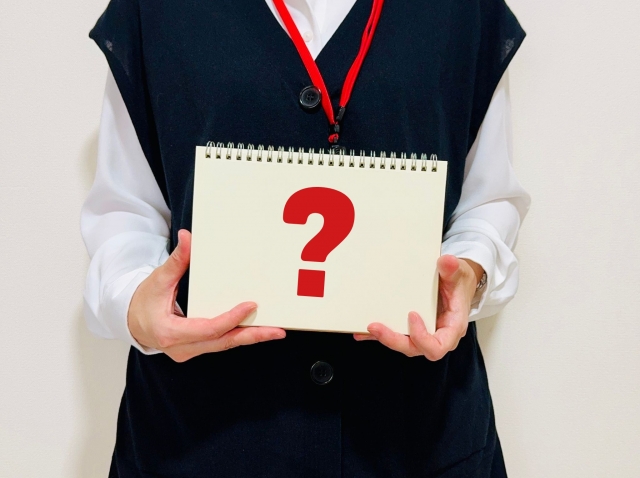
interviewer:この制度がニュースになったことで、無痛分娩に初めて関心を持った方も増えたかもしれません。制度自体がどう設計されたのか、その背景についても気になります。
市村さん:率直に言えば、やっぱり選挙が近いということが影響していると思います。来年に都議選も控えているので、ある種の“実績作り”としての側面は否めないかなと。制度設計としても、そこが透けて見えるんですよね。
interviewer:なるほど。施策のタイミングや範囲から見て、政策本来の目的よりも“アピール”の意図が強いのではないかということですね。
市村さん:そうです。本当に「少子化対策」を目的とするのであれば、制度設計がちょっとチグハグだと思うんです。今回の助成は、すでに妊娠している人が対象なんですよ。つまり、妊娠するという選択には影響を与えない。
interviewer:確かに、妊娠そのものを後押しする施策ではないですよね。
市村さん:そう。たとえば、妊娠に踏み切るかどうかで迷っている人に対してのインセンティブにはならない。しかも、東京で無痛分娩を希望するような人たちは、ある程度経済的に余裕のある層が多いわけです。東京は全国でも出産費用が最も高いエリアですから。
interviewer:ということは、むしろ「助成がなくても無痛分娩を選ぶ層」に向けての支援になっている可能性もあると。
市村さん:そうなんです。たとえば、東京に住んでいても、実家のある地方で出産した方が費用を抑えられる場合も多い。助成があるから東京で産もう、とはならないと思います。だったら、その10万円を、東京以外での出産でも使えるようにした方が理にかなっている。
interviewer:出産支援という観点で考えると、制度の整合性に疑問が残るということですね。
市村さん:はい。都の財政は潤沢ですし、たとえば「出産する人全員に10万円の支援をする」といった設計の方が、よほど公平性があるんじゃないかと思いますね。
制度が生む“有象無象”の無痛分娩、現場からの強い危機感

interviewer:今回の助成によって、無痛分娩を行う施設が増えるとしたら、医療現場としてはポジティブな変化と捉えられるのでしょうか?
市村さん:一見すると良いことのように思えるかもしれませんが、実際にはそう簡単ではありません。東京ではすでに麻酔科医が全然足りていないんですよ。そういう中で「助成が出るから」と無理に無痛分娩を導入する施設が増えると、結果的に“質の低い無痛分娩”が広がる恐れがあります。
interviewer:それは非常に大きなリスクですね。具体的にはどういう形で質が落ちてしまうのでしょうか?
市村さん:たとえば、本来であれば麻酔科医が担当すべき麻酔を、産婦人科医が見よう見まねで担当してしまうケースが増えるんです。それでも病院としては「無痛分娩をやっています」と言えてしまう。だけど、実際には専門の麻酔科医が常駐していない。これは安全性の観点から見ると非常に危険です。
interviewer:なるほど。形式的には「実施している」けど、実力が伴っていない。
市村さん:そうです。無痛分娩って、単に麻酔を打てばいいというものではなくて、分娩の経過中、何十時間にもわたって状態を見ながら調整を続けていく必要がある。麻酔科医が24時間365日常駐している体制があって初めて、安全に行えるものなんです。
interviewer:そこまでの体制を整えられる施設というのは、限られているんでしょうか?
市村さん:はい、正直かなり少ないです。今、無痛分娩を“コンサルティング”のような形で提供している業者もあって、そういうところがバックに入ると、1人の医師が複数の病院を掛け持ちしながら麻酔を行っているケースもあります。つまり、その医師がいない時間帯には、他の医師が対応せざるを得ない。
interviewer:それでは「常に麻酔科医が対応する」という無痛分娩の前提が崩れてしまいますね。
市村さん:そうなんです。無痛分娩の品質を担保する体制がないまま、助成だけが先行すると、誤った安心感だけが広がってしまう。結果として、無痛分娩そのものの信頼性が損なわれる危険性があります。
interviewer:制度のスタートによって、むしろ「質が下がる」可能性があるというのは、非常に重要な指摘ですね。
市村さん:無痛分娩の普及そのものは否定しませんが、安易に拡大してしまうと、逆に事故やトラブルが増えて、結果的に制度全体に対する風当たりが強くなってしまう。そうならないためにも、本当に必要なのは「質の担保」なんです。
医療資源の偏在と“誰が得をするのか”という構造

interviewer:制度が始まることで、現場の医療体制にはどのような影響が出そうでしょうか?
市村さん:それはもう、はっきりしていて。無痛分娩を求める人が増えることで、東京の医療資源、特に麻酔科医が一層不足します。制度によって市場規模が大きくなれば、地方から麻酔科医が東京に流れてくる可能性も高いです。つまり、地方はますます麻酔科医不足になる。
interviewer:東京一極集中が、無痛分娩の分野でもさらに進んでしまうと。
市村さん:そうですね。しかも、東京都内でも地域によって偏在が出ると思います。たとえば、都心部には大規模な産科施設が集中していますが、住宅地として発展している周辺エリアでは、そもそも無痛分娩を提供している施設自体が少ないケースもある。結果的に、助成の恩恵を受けられる人はかなり限られることになります。
interviewer:実際には、制度ができたからといって、全員が平等にその恩恵を受けられるわけではないということですね。
市村さん:そうなんです。東京都は財政的に非常に豊かです。その豊かさの背景には、千葉・埼玉・神奈川といった近隣県に住みながら、都内で働いている人たちの労働力がある。つまり、東京の税収は周辺県の人々によって支えられているとも言えるんですよね。
interviewer:確かに、都心に通勤している人の多くが、実は都外に住んでいるというのはよくあるケースですね。
市村さん:はい。でも、今回の助成制度は、そうした周辺県に住む人たちには全く恩恵がない。東京都に住んでいるというだけで線引きされてしまっている。その点で「誰のための制度なのか」という疑問は残ります。
interviewer:その制度があることで、逆に格差が広がってしまうという指摘ですね。
市村さん:そうです。特に東京で出産できるような人たちは、すでに一定の経済力を持っているケースが多い。だから、今回の制度は“声の大きい人たち”に向けた施策という印象もあるんです。少子化対策といっても、本当に困っている層に届く設計にはなっていない。
interviewer:結果的に「助成が必要な人に届かない」という制度になってしまっていると。
市村さん:はい。本当に少子化対策を目的とするならば「出産をするすべての人に一律で支援を出す」といった制度の方が理にかなっていると思いますね。現場から見ると、今の制度はとても限定的で、恩恵を受けられる人は本当に一部だけです。
“見かけだけ”の無痛分娩に注意。問われるのは病院の体制と選ぶ力

interviewer:今回の助成制度によって、「無痛分娩を導入した」と名乗る施設が増える可能性があるという話が出ましたが、それが「体制が整っていない無痛分娩」の増加につながるという懸念について、もう少し詳しく伺えますか?
市村さん:はい。実は最近、無痛分娩の導入を「外部コンサルティング」として請け負う業者が存在していて、病院側が麻酔科医を常勤で抱えていなくても、あたかも「無痛分娩ができる施設」として体裁だけ整えることができてしまうんです。
interviewer:なるほど。一見すると無痛分娩に対応しているように見えても、体制が実際には限定的なケースもあるということですね。
市村さん:その通りです。実際には、外部の麻酔医が来ている時間帯だけ無痛分娩を実施し、それ以外の時間は産婦人科医が麻酔を担当していたり、最悪、対応できない状況もあります。それでも「無痛分娩をやっている」と名乗れてしまうのが今の制度の限界なんです。
interviewer:助成制度の開始によって、そうした体制が十分でない施設にも利用希望者が集まりやすくなると、少し心配な面もありますね。
市村さん:まさにそうなんです。制度ができることで、いわゆる「必要な医療体制が整っていない無痛分娩」が市場に増えてしまう可能性があります。こういう体制では、何かトラブルが起きた時に、誰が責任を取るのかも不明確です。
interviewer:となると、利用者である妊婦さんの側が「ちゃんと体制が整っている病院なのか」を見極める必要が出てきますね。
市村さん:はい。これは本当に大事なポイントで、今後ますます「産む側のリテラシー」が問われる時代になると思います。無痛分娩を希望するならば、24時間365日、麻酔科医が対応できる体制かどうか。それを確認せずに“安心”してしまうと、かえって危ない。
interviewer:制度が整ったからといって、自動的に安全な環境が整うわけではないという現実ですね。
市村さん:その通りです。妊婦さん一人ひとりが「どこで産むのか」をより慎重に考えなければならない時代になっていますし、それをサポートする正しい情報提供がもっと必要だと思います。
「簡単にできることじゃない」。無痛分娩の麻酔が持つ特別な難しさ

interviewer:無痛分娩というと、一般的には「麻酔をかけるだけ」というイメージを持たれることもあるかと思いますが、実際にはかなり専門性の高い医療行為なんですよね。
市村さん:はい。よく誤解されがちなんですが、無痛分娩の麻酔って、ただ硬膜外麻酔を入れればいいというものではないんです。妊婦さんは通常の成人女性とは体の状態がまったく違いますし、お腹の中にはもう赤ちゃんの命もある。何が起きるかわからないという前提で、非常に繊細な管理が求められるんです。
interviewer:そして、お産には経過時間に大きな個人差がありますよね。
市村さん:そうなんです。たとえば、手術は一般的に時間の目安がある程度予測できることが多いですが、お産の場合は長いと30時間以上かかることもあります。その間、ずっと麻酔を調整し続けなければいけない。さらに、途中で帝王切開に切り替わることもありますから、その際は適切な麻酔方法への切り替えが求められます。
interviewer:無痛分娩から緊急帝王切開に切り替わった場合でも、スムーズに対応できるかどうかというのは、病院の体制や実力が問われる場面ですね。
市村さん:まさにそこです。産科麻酔に慣れていない麻酔科医にとっては、それが一番のハードルになりますし、十分なトレーニングと実績がないと対応は難しいです。
interviewer:市村さんが現場に立たれている「鎌ヶ谷バースクリニック」では、長年無痛分娩に取り組んでこられたとのことですが、体制づくりにはどのような積み重ねがあったのでしょうか?
市村さん:そうですね。うちは年間1,000件以上の分娩があり、そのうちの7〜8割が無痛分娩です。9年間ずっとこの規模でやってきて、ようやく「わかってきたな」という感覚です。それぐらい、無痛分娩というのは経験の積み重ねが必要な領域なんですよ。
interviewer:単に設備やマニュアルがあるだけでは、決して安全にはできないということですね。
市村さん:おっしゃる通りです。無痛分娩に対応するには、医師のスキル、看護師や助産師との連携、チームとしての判断力が不可欠です。そして何より、夜中でも早朝でも対応できるだけの人員体制があるかどうか。それが最も問われるポイントだと思います。
キャパはもうない。“形だけ”の導入が広がる未来への懸念

interviewer:無痛分娩の助成制度が始まることで、制度を利用したい妊婦さんが増えてくることも予想されますが、受け入れる側の医療体制には今どのくらいの余裕があるのでしょうか?
市村さん:はっきり言いますと、もうキャパシティはありません。東京で、しっかりとした体制で無痛分娩を行っている施設は限られていて、そういったところにはすでに多くの予約が集中しています。追加で無痛分娩のニーズが高まっても、すぐには受け入れられない状況です。
interviewer:体制が整っていない施設が「助成金が出るから」と急いで導入しても、現場が回らなくなってしまうリスクがありそうですね。
市村さん:おっしゃる通りです。本来、無痛分娩には24時間365日体制で麻酔科医が対応できる環境が必要です。でも、そのような人材を確保できていないまま「うちでもやってます」と言い出す施設が今後さらに増えると思います。
interviewer:麻酔科医の確保という点では、そもそも人数が足りていないのが現状なんですよね。
市村さん:はい、そこが一番大きな問題です。しかも、産科麻酔に特化した教育を受けた麻酔科医はごくわずかです。麻酔科の研修を受けられる病院の数にも上限があるので、需要が増えてもすぐに供給が追いつくわけではありません。
interviewer:それによって「形だけの体制」が横行することにもなりかねないと。
市村さん:そうですね。形だけ「麻酔科医がいる」と言いながら、実際は非常勤で限られた時間しかいないとか、その医師が不在のときには産婦人科医が麻酔を担当してしまう。そういう不安定な体制では、いざという時に対応が遅れ、母子ともに危険にさらされる可能性があります。
interviewer:それでも「無痛分娩対応の施設」として表示されてしまうのが、利用者にとってはとても紛らわしいですね。
市村さん:そうなんです。制度があることで「体制が整っているように見える施設」が増え、妊婦さん側が誤解してしまうリスクもあります。だからこそ、これからは産む側が「どういう体制でやっているか」をしっかり調べる必要がありますし、メディアもそうした点をきちんと伝えていかなければならないと感じています。
少子化対策になっていない。“エビデンスに基づく政策”の欠如

interviewer:制度が「少子化対策」として打ち出されていることに、疑問の声も上がっていますね。
市村さん:はい、私もそこが一番ひっかかっている部分です。たしかに無痛分娩は妊娠・出産への心理的ハードルを下げる可能性がありますが、この制度はすでに妊娠している人にしか適用されないんです。つまり「今後、子どもを生みたいと思って妊娠するかどうか」という意思決定にはあまり影響しません。
interviewer:少子化の原因に対するアプローチになっていないということですね。
市村さん:そうなんです。無痛分娩の助成は「出産の選択肢が広がる」ことにはつながるかもしれません。でも、それが出生率の改善に寄与するかというと、正直その因果関係は見えてこない。
interviewer:なるほど。今の制度設計では、少子化対策としての“効果検証”が難しそうですね。
市村さん:そう。政策というのは本来、EBPM——つまり「エビデンスに基づいた政策立案」であるべきなんです。実際にその施策がどれだけの効果を生むのか、客観的なデータに基づいて設計・評価される必要があります。でも今回の制度は、そこの視点がとても弱いと感じています。
interviewer:たとえば、どんな指標があれば効果が見えるようになると思いますか?
市村さん:たとえば「無痛分娩の費用が補助されることで、出産施設の選び方がどう変わったか?」「制度の利用が今後の出産意欲にどう影響したか?」などを継続的に追う調査が必要です。そういったフィードバックがないまま、ただ助成金を出すだけでは政策の意味が曖昧になってしまいます。
interviewer:医療現場の視点から見ても、もっと制度の目的や設計の精度を高める余地があるということですね。
市村さん:はい。この制度そのものを否定したいわけではありません。でも「何のための制度なのか?」「どんな効果を狙っているのか?」が曖昧なままだと、現場としても納得感が持てないんです。
誰もが安心して産める社会のために、制度ができること

interviewer:ここまでお話をうかがってきて、制度に対して懐疑的な見方も出ていますが、逆にどういった制度であれば現場にとっても納得感があると思われますか?
市村さん:やはり、一番理想的なのは「妊産婦すべてに一律で支援が届く制度」だと思います。たとえば、妊娠・出産にかかる費用を広く補助するとか、入院中のケアや産後のサポートにも目を向けるといった形で「どんな環境の人でも安心して出産できるようにする」ことが大事です。
interviewer:出産の選択肢のひとつとして無痛分娩を支援するのではなく「出産そのものに対する支援」が求められるということですね。
市村さん:そうです。今回の制度は“無痛分娩を選ぶ人”だけを対象にしているので、それ以外の人との間に不公平感が出てしまいます。でも実際には、自然分娩でも帝王切開でも、出産にはそれぞれにリスクがあって、サポートが必要です。
interviewer:たしかに、分娩方法を問わず、出産は大きな身体的・精神的負担を伴いますよね。
市村さん:そうなんです。しかも、本当に支援が必要な人ほど情報にアクセスできなかったり、制度の恩恵にたどり着けないこともあります。だからこそ「声の大きい人」ではなく「本当に必要としている人」に届く制度であってほしいと思いますね。
interviewer:制度の対象や設計のあり方を、もう少し多様な視点で見直す必要があると。
市村さん:はい。今回の制度がきっかけとなって、無痛分娩や出産の選択肢についての理解が広がるのはすごく良いことです。でも、それを本当に有意義なものにするためには、支援の幅や設計そのものが「誰のためにあるのか?」という根本から問い直す必要があると思います。
“制度の先”にある社会の変化を見据えて

interviewer:ここまで制度の課題について伺ってきましたが、とはいえ今回の取り組みが「無痛分娩」や「出産環境」に対する関心を広げるきっかけになる面もあると思います。そうした前向きな側面についてはどうお考えですか?
市村さん:そこは本当に大きな意味があると思っています。今回の助成制度が話題になったことで「無痛分娩って何だろう?」とか「どうやって病院を選べばいいんだろう?」といった関心が高まったのは事実ですし、妊婦さん自身が情報を調べたり、自分に合った出産スタイルを考えるきっかけになれば、それだけでも価値があると思います。
interviewer:制度の整備をきっかけに、妊娠・出産について“知ること”の大切さが広まっていくと良いですね。
市村さん:はい。無痛分娩に限らず、出産や子育てに関する情報って、まだまだ偏っていたり、正確に伝わっていないことが多いんです。だから、制度の枠にとどまらず「安心して子どもを産み育てられる社会ってどういうものだろう?」と、もっと広い視点で考える機会が増えてくれたらいいなと思います。
interviewer:そのためには、医療側だけでなく、行政やメディア、社会全体が関わっていく必要がありますね。
市村さん:本当にその通りです。医療者としても、もっと丁寧に情報を発信していく努力が必要ですし、制度を作る側にも、現場の声をきちんと拾ってほしい。最終的には、制度がどうあるべきかということ以上に「誰もが安心して子どもを産める社会をどう作るか?」が問われているんだと思います。
interviewer:出産を取り巻く環境が、より良い方向に進んでいくための第一歩になってほしいですね。
市村さん:はい。制度のスタートはあくまで“入口”であって、ゴールではないですから。これをきっかけに、もっと開かれた議論が広がってくれたら嬉しいです。












